


 |
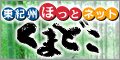 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
鯛・鯖(鯛・鯖売って) <
たい・さば(たい・さばうって) > |
<
紀北町(旧紀伊長島町、旧海山町) > |
|
紀伊長島町西長島の行事。節分の夕暮れ時、子どもたちが袋を持って「たいさま(鯛・鯖)売って」または「たいさば(鯛・鯖)売って」と言いながら、家々を訪ねていく。地域の家ではお菓子を用意しておき、訪ねてきた子どもたちに渡すというもの。
|

|
|
新しい年を迎え、今年もたくさん魚が獲れるようにと願う“叶豊漁”の祈りが、「鯛・鯖売って」の行事につながっている。節分の夜、船主の家々をまわり、「魚をようけ(たくさん)獲ってきたんやってな。私の家にも分けてほしい。」「そうか、おかげでようけ獲れたんや。売ってやろう。」こんな人々の豊漁を願い、祝う気持ちが「鯛・鯖売って」の行事になったとされる。
|

|
元々は生活の知恵の一つであったとされている。古くは猟師町でも、その日その日の生活に苦しい時代もあり、朝と昼にはおかゆを炊き、夕方にだけご飯を炊いたといわれる。それは夜間に地震や津波が起こったとき、いつでも握り飯にして持ち出せる用意のものでもあった。「朝がゆに夕めし」という言葉を古老から聞いていた故人も多い。
この「鯛・鯖売って」の行事でも戦前は、子どもたちがもらってくるものには、乾物が多かったと聞く。保存のきく食べ物が多かったのであろう。それを仏壇にあげておき、非常時に備えた家が多かったのである。年越し豆を神棚とか仏壇にあげておき、非常食としたのと似かよっている。
|

|
|
この行事を年越しの行事と強く関連づけてみる人が多い。節分を迎え、つまり新年を迎えるにあたって、過ぎし一年の悪をすべて取り去り、新しい年の幸を祈願するのである。厄除け的な色彩が強く、人々に食べ物を振る舞うことによって悪を取ってもらい、福を招き、健康な一年が送れるようにするのである。
|

|
|
戦後この行事は、一時途絶えたが復活した。猟師町の行事だったのが、昭和30年頃から西長島全体に広まった。特に10年ほど前からは盛んになっている。子どもたちは家々を回ればお菓子がもらえるとあって、最近では他の地区からも大きな袋を持ってきている。「たいさば売って」「たいさま売って」の声が聞こえ、子どもたちが平岩・松本までやってくる。いく組もの子どもたちが訪れ、町内に活気がみなぎるひと時である。
|

|
 |
参考文献 |
| |
なし |
 |
その他関連情報 |
| |
なし |
|