|
この大晦日から元旦にかけて尾鷲市九鬼町において正月梼屋行事(※)として「にらくら」まつりが開催されます。
まず大晦日の12月31日には地区内の石垣で囲われた空地(※※)のにらくら【地図】で「ひょうけんぎょう」と呼ばれる火祭りが行われます。
そして翌日の元旦には早朝から船上での豊漁祈願神楽と「にらくら」を泥田にした状態で炭の泥を掛け合う「にらくら」祭り(上の祝、角力取)が行われます。
大晦日の行事では悪病を火で焼きはらい、そして元旦の行事では黒い泥をかけあって諸病や災害をのがれるという意味があり、中世からつづく正月の伝統行事です。
是非、九鬼町の珍しい行事をご覧ください。
■大晦日の「ひょうげんきょう」の模様(スライドショー)
※ご覧いただくにはActiveXが必要です。導入できない場合はココをご覧ください。
▲トップに戻る
■元旦の「角力取」の模様(スライドショー)
※ご覧いただくにはActiveXが必要です。導入できない場合はココをご覧ください。
▲トップに戻る
<注釈>
※九鬼の正月梼屋行事
九鬼の正月梼屋行事はこのにらくら祭(12/31〜1/1)と鰤祭り(1/2〜3)をあわせたの計4日間を指します。一昔前は6日間行われていました。
※※にらくら
「にらくら」は空地といっても九鬼地区の聖地であり石垣の上には祠が祀られています。
▲トップに戻る
<日程>
○12月31日
□ほだ(薪)集め 午後
【場所】九鬼町内各地
大晦日の午後に子どもたちが「松木と米こう(買う、乞う)銭も金ももって代々良い年とらんせ」「ひょうけんぎょうに米こう銭も金ももって代々良い年とらんせ」と歌って各戸へ回って米やもちなどを供出を受けるがその際に必ず薪を2〜3本添えられることになっており、集められた薪は真巌寺下にある石垣で囲われた「にらくら」と呼ばれる空き地に運ばれ、高く積み上げられます。
□ひょうけんぎょう 19時〜
【場所】にらくら(真巌寺の下)
そして夜6時ごろに一斉に火がつけられます(これを「ひょうけんぎょう」と呼ぶ)。この火にあたると1年中風邪をひかないといわれ多くの見物客が集まります。そして19時頃、九木神社から来た神楽がにらくらの火の前で踊りを奉納しその後、町内を練り歩きます。
にらくらの薪が燃え尽きた後は一旦、水をかけて「にらくら」の中を消し炭で真っ黒な状態にします。
■「ひょうけんぎょう」の模様(YouTube動画)
■「ひょうけんぎょう」の後の練り歩き(YouTube動画)
▲トップに戻る
○1月1日
□船上での豊漁祈願神楽 6時半〜7時半
【場所】九鬼湾内
九木神社に神楽を奉納した後、鰤大敷網の船に乗って豊漁を祈願して獅子舞を行う。
□にらくら祭・上の祝 8時〜
【場所】にらくら(真巌寺の下)
元旦の朝、にらくらの内部にござを敷き円座となって共同組合長を上座に村組、配役、大梼、小梼の順で座り盃を交わし刺身や小膾などを食します。
式の最後に見物人に巻き銭を行います。
□にらくら祭・角力取 下の祝 8時半頃
【場所】にらくら(真巌寺の下)
にらくらの中の消し炭に海水をかけて泥田のようにした後、祭りの梼人達が裸になってにらくらの中へ入り相撲をとるなどして炭で真っ黒になります(真っ黒になればなるほど大漁があるともいわれています)。
その後真っ黒になった梼人達は、その後魚市場に向かい海に飛び込みます。
その後、協同組合で下の祝が行われ盃を交わし、宴が行われます。
■角力取の模様(YouTube動画)
※なお平成25年元旦には、珍しい正月行事としてこの「角力取」がNHKの元旦特集「テレビが見つめたニッポンの正月60年!」で全国生中継されました。
▲トップに戻る
※2018年12月30日掲載分
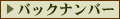 |


|