


 |
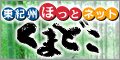 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
熊野古道という名称は、江戸時代の有名な博物学者である小野蘭山が、江戸幕府の命令で紀州の薬草調査(1801年)の時、和歌山から紀州領に入る際のルートの中に「熊野古道」という名称が見られる。この名称は今日賑やかになった熊野古道とは異なり、古い道の呼び名であったのだろうと思われる。
昭和52年に和歌山県の今の中辺路を整備するための費用として、国が補助金をだしている。和歌山県はその頃「熊野古道」という名称を使用していたようである。その当時、熊野市教育委員会の中で、文化財専門委員が三重県の古道も保存して後世に残そうと、「古道保存会」の設立を呼びかけたが、賛同を得られず立ち消えになった経緯がある。
当時は三重県側の熊野古道で「東熊野街道」や「旧東熊野街道」という文字が使用されてきた。平成7年に、現在の熊野古道である「熊野街道」「東熊野街道」「旧東熊野街道」の名称をいずれにするか、各分野の専門家が集まり協議した結果、「熊野古道」と和歌山県に合わせることになった。当時の判断は今にして思えば正解であった。出席した一員として責任を果たせたと胸をなでおろしている。
平成11年4月18日から11月6日までの間、「東紀州体験フェスタ」が開催された。この中で「熊野古道」の名称のもとに、「古道ウォーク」が実施され、紀伊長島町のツヅラト峠道から紀和町の通り峠・千枚田に至る峠道が脚光を浴びて、三重県はもとより全国的に「熊野古道」の価値が評価され注目された。このフェスタ期間中に熊野古道を歩いた人々は約14万人にも及んだ。
熊野古道の歴史
熊野の神と仏が衆生(生き物・主として人間)を助けるためにこの世に現れた。平安時代に京都で政治を執っていた天皇や、天皇の位を皇太子に譲った上皇(じょうこう)達がはるばる京都から熊野の神と仏の信仰を求めて、熊野三山に参詣した。この熊野の神と仏のお陰で長い間、天皇の政治が続き熊野三山の位が上がり、世の中から熊野が高く評価された。鎌倉時代になり天皇方の参詣がすたれたが、その後、西国三十三所の霊場参りで那智山が賑やかになり、熊野三山も活気を取り戻した。江戸時代になると、伊勢神宮へ参拝した後、熊野詣をする人々が増えた。その様子を、「蟻の熊野詣」と称して1801年には「巡礼三万人通ル」と熊野年代記に記された。
三重県側の熊野古道は「熊野参詣道―伊勢路」と称され伊勢の田丸から紀和町までの約140kmが道として残り、その中で紀伊長島町から紀和町までの約34kmに及ぶ石畳道などが国の遺跡として指定され、保存されることになった。また峠からの熊野灘の入り江の景色や、道々の自然が高く評価されてこの六月には世界遺産の仲間入りを期待されている。 |
花尻 薫(はなじり かおる)さん
<プロフィール>
自然観察会…近辺の自然観察コースを巡ること、山菜採り、キノコ狩り、他
野鳥観察会…地域を3ヶ所と決め、定期的に行っている。
アカウミガメ上陸調査…一定地域内の調査を行っている。
七里御浜の巾の測量…10年間程中旬の日に行ってきている。
2003年 地域文化功労賞(文化庁)受賞 |
|
|

